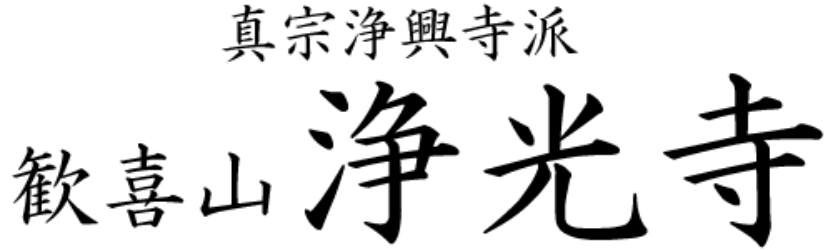四十九日を過ぎる納骨ですね
納骨とは、遺骨をお墓などに埋葬をすることをいいます。納骨は、大切な方を失ったご家族にとっても、故人にとっても、気持ちを整理し、区切りをつける大切な節目になります。
しかし、お墓が用意できていない場合や、離れがたく手元において供養している場合、埋葬方法がなかなか決められない場合など様々な理由から、納骨をされていない方もいらっしゃいます。
ところで、納骨の時期や手順には決まりはあるのでしょうか。詳しくは分からない方も多いのではないでしょうか。
納骨の時期は?
骨の時期について、特に明確な決まりはありません。
ただし、一般的には四十九日の法要の際に納骨する場合が多いようです。
しかし、お墓がない場合は、百か日や一周忌などのその後の法要や年忌法要などと合わせて行うとよいでしょう。
私たちはいつ病気やけがをしてしまったり、予期せぬ自然災害にあったりするか分かりません。
様々な理由から納骨を先のばしにされているご家族の中には、いつまでもこのままにしておけないと考えられている方もいらっしゃるかもしれません。
慌てる必要はありませんが、後悔しないように納骨の時期や埋葬方法について考えておく必要はあるでしょう。
納骨時期① 四十九日法要後に納骨する
すでにお墓がある場合は、親族一同が集まる四十九日の法要当日に納骨することが多いようです。
その場合、四十九日の法要後に納骨を行うという流れになります。
納骨時期② 火葬当日に納骨する
寺院やお墓の都合にもよりますが、火葬を終えた後、そのまま納骨することもあります。
その場合、火葬後に住職や親族とともに墓地へと移動し納骨を行うという流れになります。
納骨時期③ しばらくたってから納骨する
お墓がない場合は、四十九日には間に合わないため、百か日や一周忌、初盆など、親族が集まりやすいその後の法要や年忌法要当日に納骨することもあります。
この場合は、法要後に納骨を行います。
納骨の手順
石材店への依頼
戒名を墓石に入れる場合は、納骨に間に合うよう余裕をもって石材店に依頼しておきましょう。
埋葬許可証の用意
納骨を行う場合には「埋葬許可証(埋火葬証明書)」が必要です。
市町村役場に死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。
火葬されると、この火葬許可証に証明印が押されます。これが「埋葬許可証(埋火葬証明書)」になります。
納骨の日程調整
お墓の準備を考慮して、親族や寺院、石材店と納骨を行う日程を調整します。
納骨の日程が決定したら、親族だけでなく、故人が特に親しくお付き合いしていた人にも伝えましょう。
お布施やお供え物の準備
納骨法要では、住職に墓前で読経をしてもらうため、お布施を用意しておきましょう。
金額の目安は一般的に1~5万円ほどです。
開眼法要と一緒に依頼する場合は3~10万円が目安です。
また、故人へのお供え物として、花、果物、お茶、お菓子などを準備しておきます。
開眼法要、納骨法要
新しくお墓を建てた場合は、まず開眼法要をする必要があります。
入魂式とも呼ばれ、墓石に仏様の魂を入れるための法要です。
その後、納骨および納骨法要を行います。
法要では、住職にお経をあげていただいた後、親族が順番に焼香を行います。
会食
納骨の後にホテルなどで会食を行う場合もあります。
その場合は、事前に会場や食事の予約や、参列された方への者へ引き出物の手配しておきましょう。
会食当日は、みなさんで故人の話などをして和やかに過ごすことが故人への供養にもなるでしょう。
納骨で大切なこと ~ 人の気持ち
納骨の時期に決まりはありませんので、ご家族のみなさんが納得してから納骨することが大切です。
埋葬方法も、一般的なお墓だけではなく、永代供養墓や、樹木葬、散骨などの方法があります。
納骨時期だけはなく、埋葬方法についても故人やご家族のみなさんが納得して決めることが大切です。
残された人にとって、なかなか亡くなったことを受け入れがたいという心情を理解することは、とても大切なことだと思います。
「そんな急いで納骨しなくとも、、」
「もう少し家でお祀りしたい。」
そういう気持ちに配慮しながら、納骨されたらよろしいかと思います。