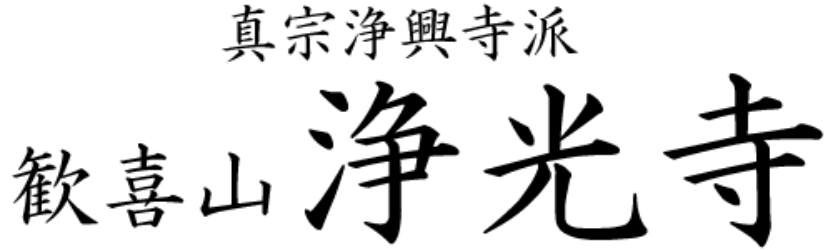喪に服す
近親者が亡くなった場合、一定期間、亡くなった人の死をいたみ、つつましく暮らすことを「喪に服す」と言います。
喪中とは
亡くなってから四十九日の間は「忌中」と言います。「忌中」は四十九日、「喪中」は一年間が目安「忌中」は、不幸があった時から始まり、仏式では四十九日、神式では五十日祭、キリスト教では一カ月たった召天記念日または五十日祭までとされるのが一般的です。
忌明け
「忌明け(きあけ)」は仏式で四十九日の法要を終えた後のことを指し、法要を「忌明け法要」、香典返しや満中陰志を「忌明け返し」と呼ぶこともあります。
喪中
どの宗教も一年間とされることが多いようです。
かつては、故人との関係によって忌中・喪中の期間に決まりがありました。
最近では忌中、喪中の過ごし方も変わってきています。
忌中までは遊興は控えましょうと一定期間亡くなった方の死を悼み、喪に服して身を慎むのがしきたりなのです。
結婚式披露宴や祝賀会などは控えるのがマナーとされます。
故人が生前楽しみにしていたお祝いや遺族にとって大事なことであれば柔軟に考えるケースは多いようです。
感想
人によって、亡くなった方への想いは違うものです。
人によってその人の感情の在り方も異なります。
何時までの悲しい想いを引きずってしまう人もいれば、ツライ気持ちはそのままにして、気分を転換して、立ち上がるために忘れようとする人、その人その人によって思いはまちまちです。
だから人間なのだし、それが感情なのだと思います。
喪をどう過ごすのか?
昔は世間体がありました。
ある一定期間、喪に服しておとなしくしていないと、近親者から責められることもあったことでしょう。
いまは、違います。自由にできる時代です。
たとえば、最愛の母を亡くしたとします。
長い間、お母さまのことを想って、なかなか日常生活に戻れない。
仕事が手に使いない。
気持ちはわかります。
でも、そうしたあなたの姿勢を天国から見ているお母さまからしたらどうでしょうか?
きっと、心配になってしまうと思います。
1週間くらいは、おとなしくしているにせよ、さっと、気分を変えて日常生活に戻る。
天国のお母さまの安心させてあげてください。喪は長くおとなしくしているというのではなく、お盆やお彼岸など、タイミングごとに思い出して、偲ぶ、懐かしく想う、有難く思う、感謝する気持ちが大切なように思います。